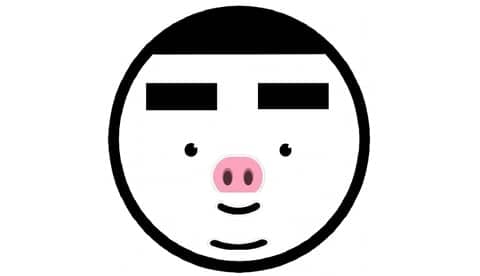良い日であって欲しいと願えば願うほど
暗闇の中で遠くにある赤色灯が薄ぼんやりと周辺を照らし、現在の特異な状況を教えてくれる。体を固定するためのロールバー。頭上のレール。半宙吊りとなった乗員たち。そしてレールから外れてしまっている先頭の筐体車両は、稲穂のようにしなだれ、自重に耐えようとみしみし音を立てている。
悲鳴や怒号が全く聞こえないわけではないが、どんな些細な切っ掛けで状況が最悪なものになってしまうのか分からない中では、押し黙っている者が多数を占めた。そんな緊張感を強いられるシチュエーションで、大戸春人はゆっくりと目を閉じ、小さく息を吐く。
彼には妹がいる。隣に座って手を繋いでいる少女、大戸理子がその人である。妹と手を繋ぐのなんて何年ぶりだろうと思いながら、ここまでに至る経緯を思い返す。
大戸家は毎年妹の誕生日になると、家族揃って出かけるようになっていた。小さな頃はファミリーレストランで食事程度のものだったが、年を経る毎にバージョンアップしていった。昨年は祖父が亡くなったこともあって、ささやかなものになったが、今年はその分も取り返そうなんて勢いもあって、泊まりがけで遊園地に遊びに行くことになった。
ファンシーな雰囲気に彩られた遊園地は多数のアトラクションを擁しており、この屋内施設にある揺り籠型のライド系アトラクションは施設でも1,2位の人気を誇るものだった。
人気のアトラクションはその待機列も長蛇となる。事前に優先チケットを取得していれば、スムーズに搭乗できることもあって、両親が先んじてチケットを取得し、自分と妹がそれを追いかけ、入れ替わるように搭乗していくという流れで消化していった。
目を輝かせながら、それぞれのアトラクションの素晴らしさを滔々と語る妹を横に、春人は内心退屈な気持ちでいた。
妹の誕生日を喜ばしく思ってないなんてことはない。ただ、自身の誕生日の時に、同じような熱量で家族が祝ってくれているかというと、決してそうではなかった。
そのことについて恨みがましい気持ちがないと言えば嘘になるが、半ば諦めに似た納得感というものもあった。
妹は出来過ぎている。平々凡々な家庭である大戸家にとって、妹の存在感は少々度が過ぎている。これは兄の贔屓目、家族の贔屓目なんてレベルを超えていて、歳を重ねる毎にその評価は大きくなり、ご近所から町内レベルへ。そして学区レベルへと広がっている。
この先、どこかでそれも折れるのかもしれない。ただ、大戸春人という少年の見聞きする世界に限っては、そういった可能性は微塵も感じられなかった。
そんな妹の誕生日にアトラクションが事故を起こした。身の危険から隣で震えている妹に、大丈夫だよと声を掛けたが、これは兄としての立場から出た言葉でもなく、気休めから出た強がりでもない。
妹がこんな所で死ぬわけがない。妹がこんな所で致命傷を負うわけがない。
妹は小さい頃からいつだって周囲の期待に応え、これまで完璧とも言える人生を歩んできたのだから。誰からも愛される妹を、それだけの資格・器量を持ち合わせた妹を見捨てる神なんているはずがない。
危機的な状況を目の当たりにしても、どこかで自分たちはきっと助かるのだろうなんて思っていた。
が、そんな期待はあっさりと裏切られた。
けたたましい音が聞こえてきたと同時に、自身の体が落下していく感覚に襲われる。
右手にある妹の温かみと共に――。